こんにちは。今年も残暑厳しいですが、皆様どうぞ体調にお気を付けください。酒ミュージアムの酒資料室では、8月に引き続き9月13日から「世界のみなさんこんにちは 日本酒と博覧会」展を再開します。そこで、今回は内国勧業博覧会を、次回10月分で万国博覧会を取り上げていきたいと思います。
日本国内での博覧会開催は、明治4年(1871)の京都博覧会が最初ですが、政府主導の本格的な規模で開催された初めての博覧会は内国勧業博覧会になります。明治10年(1877)の第一回、明治14年(1881)の第二回、明治23年(1890)の第三回は、東京の上野公園で開催され、明治28年(1895)の第四回は京都岡崎公園、明治36年(1903)の第五回は大阪天王寺今宮で開催されました。

-800x574.jpg)
内国勧業博覧会の会場には、日本全国の道府県から工業・農業製品・美術品が集められました。第一回内国勧業博覧会に合わせて制作された三代歌川広重による「大日本物産図会」は、それら産品の生産の様子を描いた錦絵揃物です。摂津国からは日本酒が選ばれ、製造・出荷の様子が描かれています。また、内国勧業博覧会では優れた製品の出品者に賞が与えられており、清酒を出品した中ではやはり江戸時代以来の酒造先進地である兵庫県の出品者の受賞が多くみられます。

では、会場の様子についてみていきましょう。第二回の会場の様子を描いたものが、「博覧会見物の心得」です。注目したいのは会場を描いた上に記された文言です。ここには、見学に来る人々に向けた会場でのルールを記しています。第一条では、入門切手(チケット)を購入すること、但し土曜日は3銭、日曜日は15銭、その他は7銭とあります。曜日によってかなり価格に違いがあるのは当時の生活習慣を知る上で興味深いところです。第二条では観覧規則を心得て入場するよう注意喚起。第三条では手荷物を必ず門外の預け所に預けるよう促しています。第四条ではおすすめの見学順路を提示し、第五条では本館・その他の特徴を紹介しています。
最後の第六条は、「凡そ見物するには務(努)めて自分稼業の便(頼)りとするを心がくべし、その記録を心に留んとするには其出品人名を忘れざる事を寛容とす」とあり、内国勧業博覧会の趣旨を踏まえた条文となっています。明治政府は会場に全国の優れた製品を集めることで、多分野間の交流によるイノベーションが起きたり、他地域の生産者が展示品を参考に品質向上などに取り組むことを期待していたと考えられます。ここで受賞した白鹿をはじめ灘の酒造りは全国の目標になったとも言えます。

今回は内国勧業博覧会と日本酒についてご紹介しました。来月の万国博覧会についてのコラムもぜひご覧ください。どうぞよろしくお願い申し上げます。



より-scaled.jpg)





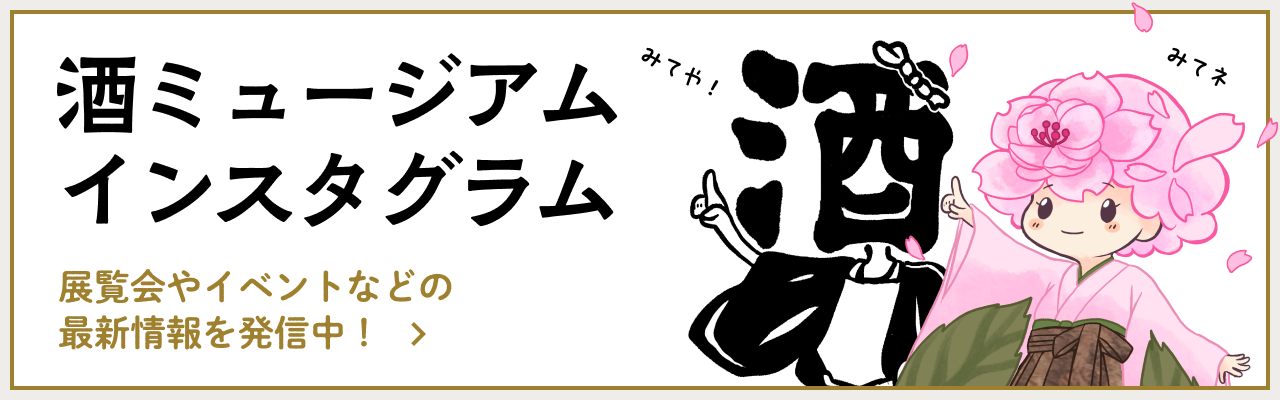


西宮自慢のお水やで!