こんにちは。7月に入り、今年も子どもたちの夏休みが近づいてきました。夏休み期間の初めには海の日があります。今月は、「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」ために設定された海の日に因んで船についてご紹介していきます。
酒トークでは、これまで江戸時代の樽廻船について何度かご紹介してきました。その後近代に入ると、辰馬家では西洋式の帆船や蒸気船を購入して海運業を継続していきました。前回のマッチ・前々回のレンガ以上に力をいれたのが、この海運業でした。

江戸時代に酒やその他物資の輸送に忙しかった樽廻船は明治に入ってほどなく姿を消していきます。これは西洋式帆船や蒸気船が日本でも運用されるようになったためです。近代化を推し進めたい明治政府により、明治18年(1885)には従来の樽廻船のような和船(500石積以上)の建造が禁止されます。この動きに対し、西洋式帆船や蒸気船は建造費・購入費が多額に上ることから、和船の長所を西洋式帆船に取り入れた折衷型の船舶も建造されました。

辰馬本家酒造では、江戸時代末期から明治初期にかけて従来型の樽廻船を所有していましたが、明治11年(1878)以降西洋式帆船を所有して酒荷輸送を行うようになります。西洋式と言っても従来の和船同様に帆船であったため、大阪―東京間の航海日数が劇的に変化するといったことはなく、記録では10数日を要する事例が多くみられます。
これら西洋式帆船とともに明治以降登場するのが汽船です。こちらは蒸気機関を動力に外輪やスクリューを回して進むため、風向きに拠るところが大きい帆船と比べ、円滑に運航することができました。酒ミュージアムの史料には、明治初期に大阪―東京間を5日程度で結んでいたことが記されており、迅速な輸送が可能になったと考えられます。

こうした、汽船の運用は岩崎家の郵便汽船三菱会社や渋沢栄一等による共同運輸が大規模に行っており、明治17年(1884)からは灘酒の輸送を、郵便汽船三菱会社と共同運輸が合併して誕生した日本郵船が行うようになります。一方辰馬本家の所有する船舶は酒以外にも、瀬戸内海の塩、九州の石炭、各地の米の輸送にあたったとみられます。
今回は明治期の辰馬本家の海運業についてご紹介しました。その後大正期には辰馬汽船株式会社を設立し、第二次世界大戦終戦後に手放すまで海運業に関わっていきました。今後の酒トークでは辰馬汽船のご紹介もできればと思います。来月もよろしくお願いします。





-1-scaled.jpg)

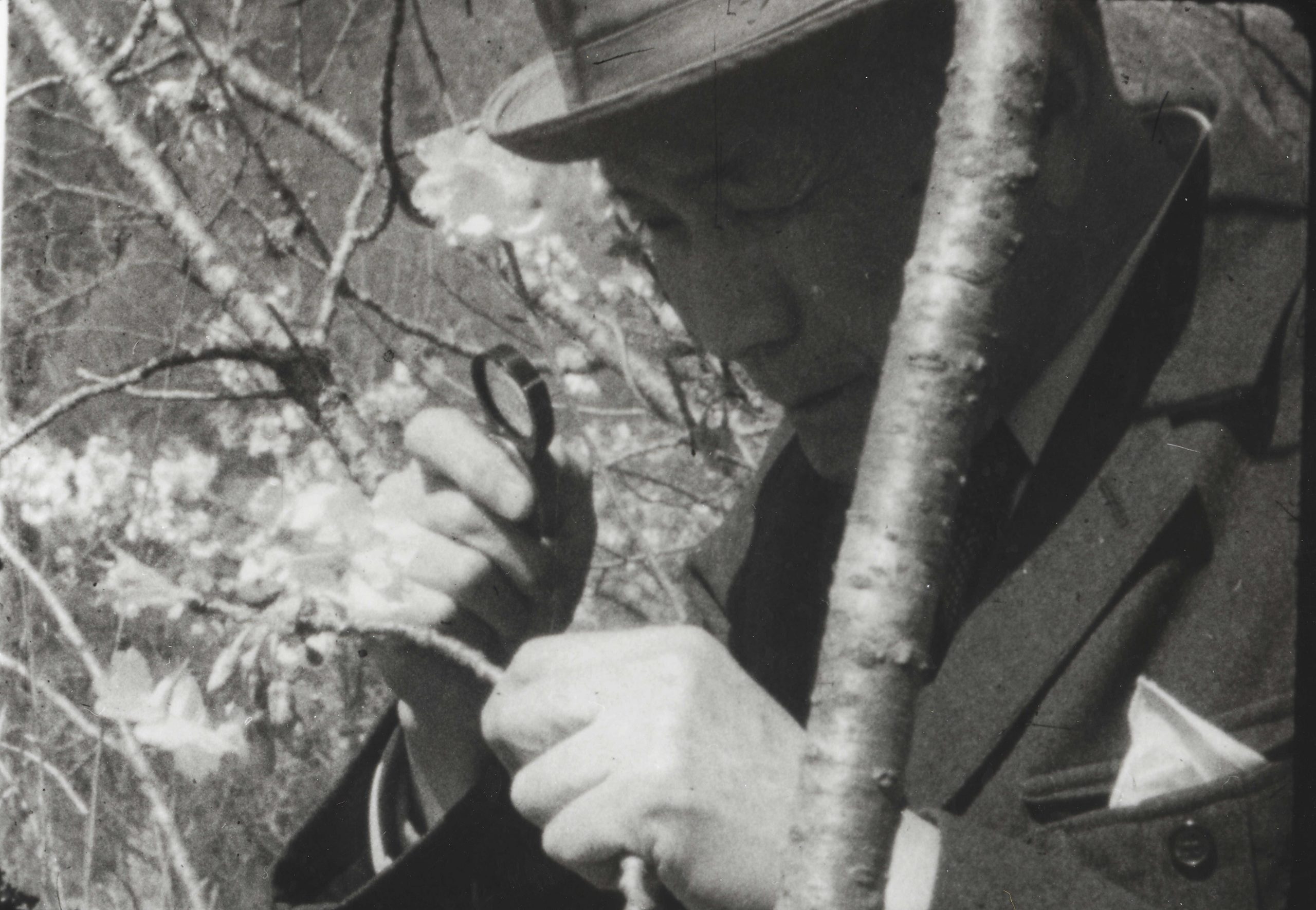

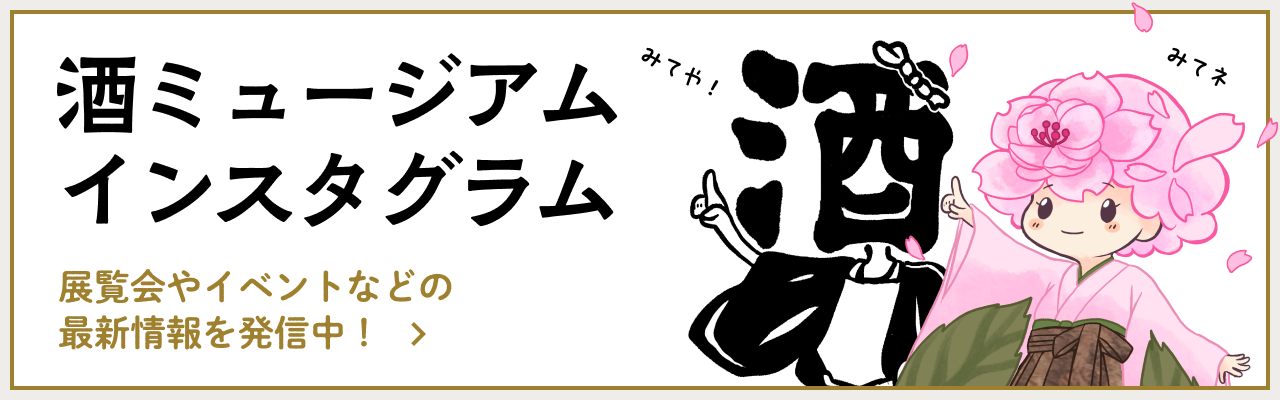


今や世界のSAKE!